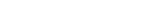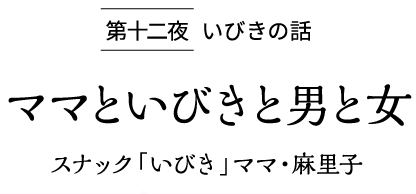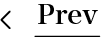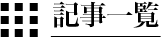開店前のスナックいびき。駅前のスーパーで特売になっていた新じゃがを購入したママは、鼻歌まじりに突き出し用の肉じゃがの仕込みをしていた。
トントンと小気味よくまな板を鳴らす音が響く店内。いつもと変わらないスナックいびきの1日が今日も始まるはずだった。
扉の開く音が聞こえたママは、少し面倒くさげに視線を上げる。開店前だっていうのにいったい誰かしら。
入ってきた男と目が合った瞬間、まるで音が聞こえてくるのではないかと思うほど自分の鼓動が大きくなるのが分かった。
「久しぶりだな、麻里子」
前触れなく現れたその男は、ママこと麻里子の元夫・真一だった。
別れてかれこれ10年は経ったのかな、元夫の姿を見てすぐそんな計算をする自分が女々しく感じる。
「悪いな、開店前で忙しいところに。ちょっと浩之のことで、どうしても直接話しておきたいことがあってさ」
浩之は真一とママの一人息子だ。動揺していることを勘付かれないよう、ママはてきぱきと動きながら2人分のお茶を入れる。湯呑みのひとつを真一の前に置いてからカウンターを出た。正面に立つよりは、隣に座った方が顔を突き合わせずに済む。
真一は目の前に置かれたお茶に口をつけると、ぽつりとつぶやいた。
「『いびき』って名前にしたんだな。雰囲気の良い店じゃないか」
浩之の名前が出たからてっきりその話が始まるかと思ったが、そうでもないらしい。ママも、気持ちを落ち着けるために、会話に付き合うことにした。
「まあね、これでもけっこう繁盛してるのよ。名前のせいで毎晩いびきの相談が多いんだけどね」
「お前がいびきのアドバイス?」
「そうよ。誰かさんのおかげで、いびきに悩む人の気持ちはよく分かるから。それに必死で勉強したことが今になってとっても活きてるわ」
二人が別れたのは真一のいびきが原因だった。
慢性的な鼻炎を持っていた真一は、日ごろからいびきをかく方だったが、花粉症の時期は特にひどかった。それだけなら季節的なものだと我慢もできたかもしれないが、仕事の付き合いだと言っては頻繁に酔っぱらって帰ってきて、そのたびに高いびきをかいて寝ている姿を見て、真一への愛情が冷めていくのが手に取るように分かった。
その後も繰り返されるいびきが原因で寝不足になり、疲れとイライラからけんかを繰り返して、離婚を決意したときにはもう完全に気持ちが離れていた。
その頃のことを思い出して、ママはほろ苦い気持ちになる。
「昔のことでも思い出してたのか?」
左から聞こえてくる声は、相変わらずの鼻声だ。
「わたしの勝手」
「あの頃は迷惑かけたな」
「思ってもいないくせに、取ってつけたようなこと言って」
「いや、本心だよ。でも、当時はまだ若かったせいもあって、お前がいろいろ調べてくれたり、試してくれたりすることに対して、感謝よりも『たかがいびきで大げさな』って思いが強かったんだ」
「そうでしょうね。ICレコーダーやアプリを使っていびきを録音したのもわたし。湿度が鼻づまり対策になるからって、加湿器と湿度計を置いたのもわたし。マットレスと枕を買い替えたのもわたし。夜中に起きて横向きに寝させてあげたのもわたし。それから」
「分かった! ほんとに悪かった、この通り!」
カウンターに額をつけて大げさに謝っている姿を横目で冷静に眺め、ママも少し溜飲が下がった。
「そういえばさ、寝ているときに『息が止まってたよ』って起こしてくれたことがあったろ。あのときは、わざわざ病院なんて、って思ってたんだけど、実はこの前行ってみたんだよ。お前がさ、いびきの背景には睡眠時無呼吸症候群や病気が隠れてるかもしれない、って何度も言ってたのを不意に思い出しちゃって」
「なによ、ずいぶん今さらね。で、結果はどうだったの?」
「問診で、『寝ている最中に息が止まったり、かと思ったら急に大きないびきをかくことがあるかも』って言ったら、家で検査することになって」
「あら、それって」
ママは、それが睡眠時無呼吸症候群の特徴に合致していることに気がつき、前に向けたままだった視線をようやく真一の方へ向けた。
「まあ、結果的には睡眠時無呼吸症候群じゃなかったんだけどね」
あっさりと否定する真一に拍子抜けし、多少でも心配した自分を後悔した。
「CPAP療法にマウスピース、あと外科的手術が治療法にはあるんだってね。俺も怖くなっていろいろ調べたよ。全部取り越し苦労だったけどさ」
「どう? 少しはわたしの気持ちが理解できた?」
聞き取れないほどの小さな声で真一は、すいませんでした、と言ったようだった。
「でも、いびき自体はまだ治ってないんでしょ? もしかして鼻チューブとかしてる?」
「そうなんだよ。さすが麻里子! よく分かったな。試す前は『こんなの絶対痛いよ』と思ってたんだけど、実際入れてみたらほとんど痛みはないし、違和感もなく使ってるよ。おかげでぐっすり寝れるし。浩之からも、鼻チューブを使い出してからおやじのいびきが聞こえなくなった、って言われたしさ。俺も今じゃ立派な鼻チューバーだよ」
「なにが鼻チューバーよ。ユーチューバーじゃあるまいし」
そのくだらない発言に、思わず笑いがこぼれてしまう。そういうところに惹かれてた時期もあったっけ。昔の記憶を探りかけたが、それよりも浩之の名前が出てきたことで、今日の本題を思い出した。
「それで、浩之のことだけど、なにかあったの?」
浩之は離婚後真一が引き取り、立派に育て上げてくれた。この春に大学を卒業したばかりの22歳だ。
「ごめんごめん、つい話が脱線しちゃったな。実はさ、あいつ今付き合ってる彼女ともうすぐ同棲するんだって」
同棲、その単語を聞いてママはピンときた。
「なるほどね、この間の電話はそのためだったのね」
「なんだ、知ってたのか」
「ううん、私が聞いたのは引っ越すってことだけ。でも、なぜかいびきの相談もされたの。俺の友達なんだけど、とか、なんか変な相談だったからおかしいなとは思ってたんだけど、今の話を聞いてつながったわ。彼女と同棲するから、自分のいびきが心配だったのね。それならそうって、はっきり言えばいいのに」
「そういうことか。あいつ、俺に顔が似てるもんな。お前に似てくれれば、もっとイケメンだったのに」
「たしかに。あなたもそうだけど、骨格的にはいびきをかきやすいタイプかもね」
「俺たちみたいにいびきが原因で破局、なんてことにならなきゃいいけどな」
縁起でもないことを言う真一を軽くにらみ、ママは自信たっぷりに言い切った。
「なーに寝言みたいなこといってんのよ。あの子とあなたは全然違うから大丈夫」
首をすくめて舌をペロッと出す仕草は、あと20年若かったらかわいいと思えたかもしれないが、50歳を過ぎたおじさんでは、苦笑いしか浮かべられない。
「で、あいつ、近々結婚も考えてるんだって。お前にも報告したいって言ってたよ」
「ふ〜ん、あの子が結婚ねぇ」
「まだいつになるかは分からないけど、結婚式、二人で出たら喜ぶんじゃないかなと思って」
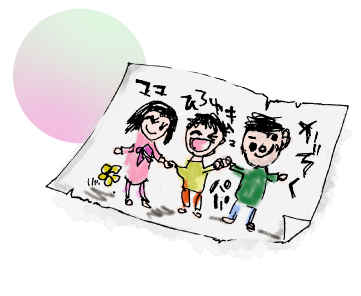
急な展開に、また鼓動が大きくなるのを感じた。
「…どうかな。考えておくわ」
「そうか」
真一は、湯呑みの底に少しだけ残っていた緑茶を飲み干すと、そのまま席を立った。
「開店前にいきなり押しかけて悪かったな」
「ホント迷惑」
「そういうところ、昔から変わらないな」
「余計なお世話よ」
憎まれ口をたたきながら、でもどこか気持ちがほぐれていくのを感じた。
じゃあまた、そう言ってドアに向かって歩いていく真一の後ろ姿を見ながら、無意識に微笑んでいる自分に気づき、ママはキリッと口元を引き締めた。
出会い、別れ、仕事、友情、恋愛、大切な人との大切な暮らし。人生が深まれば、それだけ多くの悩みや困難に直面する。いびきもその一つだ。でも、悲観する必要なんてまるでない。幸せのかたちがたくさんあるように、いびきの対処法だってたくさんあるのだ。
しばらくすると、常連さんたちの笑い声とともに、いつものようにドアが開いた。
「いらっしゃい」
完